
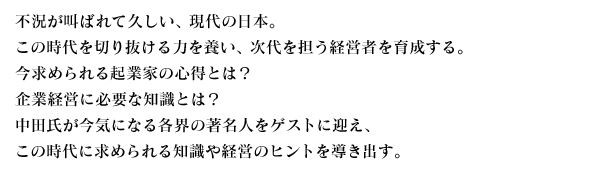

中田
武市さん、今日はお忙しいところお越しいただき、ありがとうございました。このコーナーでは、これからの日本を担っていく、中小企業の経営者や若手経営者の方々への道標となるようなお話を、成功された経営者の方々にお聞きすることを目的としています。
今回はその対談コーナー第1回ということで、はじめ良ければすべてよしという風に思っていますので、よろしくお願いします。
武市
こちらこそ、よろしくお願いします。
中田
早速ですが、武市さんはこれまで株式会社スクウェア(現スクウェア・エニックス)、株式会社ドリーミュージックをはじめ、様々な企業で代表取締役社長を務めてこられました。キャリアのスタートは高知の四国銀行だったそうですね。
武市
そうですね。大学を卒業後、家庭の事情で実家のある高知に戻ることになり、地元の四国銀行に入行しました。
中田
銀行員として勤めた後、株式会社スクウェアで代表取締役社長に就任していますね。その経緯を教えていただけますか。
武市
当時、私はベンチャー企業の開拓などを中心に行っていまして、スクウェアは取引先の一つでした。スクウェアはもともと徳島の方が創業した会社で、四国銀行がメインで取引をしていました。
私が同社に関わるようになった当時は、ファイナルファンタジー(以下FF)の第三作が発売になった頃。当時は開発費も銀行が融資できる範囲でやっていました。
しかし、ソフトが爆発的にヒットしていくにつれ、徐々に開発規模が大きくなっていきました。そうすると開発期間も長くなるし、開発費もかさみます。そんな矢先、会社から「お前、ベンチャー、ベンチャー言っているし一回スクウェアに出向してこい」と言われて、出向することになりました。
中田
なるほど。いまやゲーム業界でも絶対的な存在感を示しているスクウェアですが、その初期の段階から銀行員として関わっていたということですね。当時スクウェアは、まさに成長期とも言える時期だったと思うのですが、どんな印象を受けましたか。
武市
いざ、会社の中に入ると若い人がダイナミックに経営していることに驚きました。銀行を守りの経営とするならば、スクウェアは完全に攻めの経営。銀行では新しいことがなかなかできない風土がありましたが、スクウェアでは若い人たちがその日に議論をして、その日に答えを出していきました。次々と新しいことに取り組んでいましたね。
当時、ゲーム産業は規制もなかったので、国も誰も守ってくれないような状況。しかし、裏を返せば何をするにも制限はありませんからね。自分たちで考えて、自分たちで行動して世界と戦う必要があったのだと思います。
そういった、自由でチャレンジ精神に満ちた雰囲気がとてもよかったですね。
中田
やはり、日本を代表するゲームソフトを産み出すぐらいですから、相当な勢いがあったんでしょうね。
その後、一度銀行に戻られて、1996年にふたたびスクウェアに戻り、代表取締役に就任されたということですね。
武市
そうですね。出向が終わる頃には、年商160億、経常利益40億円程度には成長していました。1994年に店頭登録をして、一度銀行に戻りました。
その後、1996年に「社長として戻ってくれないか?」という打診があり、正式に代表取締役に就任しました。当時は、ちょうどプレイステーションが世に出て正に成長していた時期です。
私は銀行出身者として、夢と才能がある人たちを、少しでも応援したいという気持ちで引き受けました。

中田
スクウェアの社長時代には様々な事業を展開してきたと思いますが、ご自身がもっとも印象に残った仕事はどんなものでしょうか。
武市
FFのグローバル化に成功したことでしょうか。
スクウェアはFF6まで、超ドメスティック企業だったんです。日本では、250万本とか売れるのに海外に行くと数十万本しか売れませんでした。そこでFF7からは海外で販売する際、ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品として販売する戦略を敷きました。これには、社内でもかなりの反発が起こりましたね。
しかし、その結果北米で一気に200万本以上が売れるようになり、ヨーロッパでも100万本を突破するなど大成功を収めました。その後は、海外でも日本に匹敵する売り上げをあげるようになり、一気にFFのグローバル化を果たすことができました。
中田
「世界のソニー」のブランドを借りたということですね。
ちょうど、武市さんが社長をされていた頃、FFのフルCG映画にも取り組んでいましたね。確か、当時カルビーにも協賛のお願いが来ていましたよ。
その後、スクウェアを退任され、株式会社ドリーミュージックの設立に携わるわけですね。
武市
スクウェアの会長時代から、新しいレコード会社を作りたいという相談を受けていました。経営に関するアドバイスをしていた流れで、自然と「代表者になってくれませんか?」という話に。
当時、音楽事業というとコンピレーションアルバムを出すような企画物が多い時代でした。しかし、やはり新しいアーティストを発掘して育てていかないと、ビジネスは掛け算にはなりません。企画物は単発で終わりますが、一人のアーティストが有名になれば楽曲も売れていきます。
ドリーミュージックは、設立当初からそういったコンセプトがしっかりしていました。また、当時は配信事業の黎明期。他のレコード業界の人たちは、CDが売れなくなるという理由から配信事業には消極的でした。しかし、私たちは「今後、必ず配信の時代がくる」と考えて戦略を練っていたんです。
また、ドリーミュージックはコンテンツホルダーであり、コンテンツプロバイダーでもあったので、配信をしている以上、コンテンツはオープンプラットフォームでどこにでも出すことを徹底していきました。
中田
創業時から会社としてのビジョンが明確だったことや、次の時代を見据えた上での戦略が実を結んだということですね。


